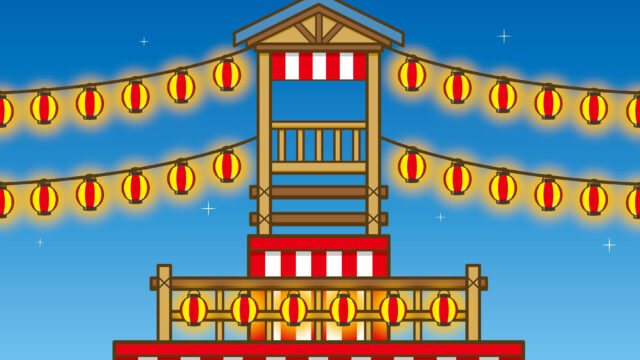入院闘病記(開放病棟) コーヒーが飲みたい! 第2話

僕は急速に、開放病棟の自由な雰囲気に、馴染んでいった。
ご飯は美味しい、仲間もいる、外出も出来る。
正に開放病棟は僕にとって、住み心地の良い天国だった。
そんなある日のこと。
先日、閉鎖病棟から開放病棟に移って来た渡辺広木さんが、僕の所へやって来た。
「ねえ、ちょっとこの近くにあるららぽーとっていう、ショッピングセンターに行ってみない?」
「ええ、何か面白そうですね。行きましょう」
僕がそう答えると、丁度廊下の向こうから歩いてきた、坊主頭の人が、大声で話しかけて来た。
「あ!ららぽーと?俺も行く!俺、樋口渉。ららぽーとのことなら、何でも俺に聞いてちょ!ららぽーとでの裏技、何個も知ってんだ。ささ、行こう!行こう!」
こうして僕と渡辺さん、樋口さんの三人で、ららぽーとに行くことになった。
ららぽーとは池田病院から、歩いて五分位の所にある、巨大商業施設だ。
飲食店、書店、スーパー、ファーストフード店、家電量販店等、三十を超える店舗が、軒を並べている。
樋口さんは大股で歩きながら、自己紹介を始めた。
「俺、樋口渉。池田病院入院歴十年。彼女無し。友達無し。舎弟は金田庄司。池田病院に入院する前は、何でも屋をやってたんだ。部屋の掃除に蜂の巣の駆除、どぶ掃除にご老人の介護まで、何でもやったな。軽トラック転がして、日本中どこへでも行ったもんだな。あの頃は若くて、怖い者知らずだったな」
渡辺さんが口を挟んだ。
「樋口さんカッコいいから、まだまだ現役バリバリで行けますよ!早く退院して、女作っちゃえば良いんですよ」
「退院か……どうやったら、退院できるの?」
「そりゃあ、主治医と話付けなきゃ駄目ですよ。一発、主治医にガツンと、かまさないと駄目ですよ!」
渡辺さんは、興奮気味に言葉を返す。
樋口さんが、遠い目をして口を開く。
「ひでまるさん、渡辺さん、俺はもうここに、十年も居るんだよ。十年は長い歳月だよ。俺は最初、池田病院と外の世界との間にある壁を嫌い、怖れていたが、段々とその壁に親しみを覚え、頼り、今では守ってもらってる気がするんだよ。不思議なものだよ。退院か……。一日も早く退院したいという気持ちがある一方で、外の世界で上手くやっていけるかどうかという不安、恐怖心が強くあるのが、正直なところさ。それより、こんな湿っぽい話は置いておいて、俺が最高に美味しいコーヒーを、御馳走するよ。御馳走するっていっても、俺がお金出すわけじゃあ無いけど。ま、行けば分かるよ、ふふふ」
何やら、意味深な笑いである。
歩いて五分ほどで、ららぽーとに着いた。
僕たち三人はショッピングセンター内を、一般の客たちに負けず劣らず、堂々と胸を張って歩いた。
誰も僕たちを、重度の精神障がい者だとは思わないだろう。
樋口さんが大声で言った。
「これから『カルディー』っていうコーヒー専門店に行くよ。誰でも店頭で、お客なら一杯、コーヒーを無料で貰えるんだ。またそのコーヒーが、美味しいのなんのって!一度飲んだら、病みつきだね。まあ、万事、俺に全て任せな!」
僕たち三人は樋口さんを先頭に、「カルディー」の店頭に向かった。
店頭には小さなテーブルが、一脚置かれており、その上に小さな紙コップが置かれていた。
その紙コップの中には、茶色い液体が、五分目位まで満たされていた。
小さなテーブルの横には、「カルディー」という店名のロゴが入った、赤い帽子を被った、若くて綺麗なお姉さんが立っていた。
そのお姉さんは周囲を見回しながら、大声で叫んでいた。
「コーヒー、いかがですか?コーヒー、いかがですか?」
僕たち三人は、お姉さんの前に躍り出た。
樋口さんが言った。
「ねえ、コーヒー一杯ちょうだい!」
お姉さんの視線が、樋口さんをしっかりと捉えた。
そしてその瞬間、あからさまに顔色が変わった。
「あら、ごめんなさい。丁度、コーヒー切らしちゃったみたい。また明日のご来店をお待ちしています。さようなら!」
どうやらこの店員、樋口さんのことを知っている様だ。
樋口さんが、すかさず言い返した。
「コーヒーなら、そこのテーブルの上にあるじゃないか!それにそのポットの中にも、まだたんまりと、コーヒーが入ってるんじゃあないのか?何だお前、要するに、俺に飲ませるコーヒーは無いってことか?」
すると、お姉さんは鬼の形相で、僕たち三人を睨みつけてきた。
「あんたら、どこの馬の骨か知らないけど、毎日毎日仲間を連れてきて、店の商品は何一つ買わないで、コーヒーだけただ飲みするつもりでしょう!こちとら、商売でコーヒー配ってるんだよ!乞食はお呼びじゃないよ。しっしっ、あっち行った、あっち行った!」
これで、大体の状況が分かって来た。
樋口さんは毎日の様に、ここ「カルディー」に来て、コーヒーを飲み逃げして、店員たちに完全に顔を覚えられていたのである。
要するに、「カルディー」のブラックリストに、載っていたのである。
樋口さんは、「フン!」と鼻を鳴らすと、負けを認め、
「ひでまるさん、渡辺さん、行こう!」
と言って、二階へ上がるエスカレーターに乗った。
僕と渡辺さんは、只々、後に付いて行くしかなかった。
樋口さんは意気消沈した様子も無く、やんちゃな笑顔を、顔一杯に浮かべていた。
「このままじゃあ、俺は終わらないよ!俺には、裏技があるんだ。まあ、付いて来な!」
僕たちは、三階までエスカレーターで上がった。
三階には飲食店、書店、家電量販店、NTTドコモ等が、店舗を構えていた。
飲食店はラーメン屋、カレー屋、寿司屋、マクドナルド、長崎ちゃんぽん等、より取り見取りだ。
やはり、精神病院の入院患者に、ショッピングセンターは刺激が強すぎる……。
僕は何だか、クラクラ眩暈がしてきた。
樋口さんは、どんどん奥へと進んでいき、ビックカメラに入って行った。
僕の横で渡辺さんが、不安そうに呟いた。
「樋口さん……電気屋さんで何をするつもりなんだろう?」
僕たちも樋口さんの後を追って、店内へ入った。
店内は、電化製品とお客さんで埋め尽くされていた。
周りを見渡すと、店内の右隅に広々としたスペースが取ってあり、そこに丸形のテーブルと、自動販売機が置いてあった。
僕たち三人は、そのスペースへと近づいていった。
どうやら、樋口さんの目的は、あの自動販売機らしい。
近づいて良く見ると、それは大きなコーヒーメーカーの機械だった。
ボタンを押せば、自動で紙コップにコーヒーが入り、それを飲めるという訳だ。
樋口さんの狙いは、正にこのコーヒーだった。
しかし、このコーヒーは電化製品を買いに来たお客さんに、サービスする為のコーヒーだ。
普通の良識ある人間ならば、お客でも無いのに、勝手に飲むことは出来ないだろう。
しかし、精神病院に十年も入院していると、良識など何処かへ、吹き飛んでしまうのだろう。
樋口さんは何のためらいも無く、コーヒーメーカーを慣れた手つきで操作して、勝手にコーヒーを飲み始めた。
そして僕たち二人分のコーヒーを、紙コップに注ぎ始めた。
「おう、何ボケっと突っ立ってるんだよ!こっちに来て、一緒にコーヒー飲もうよ!」
樋口さんは上機嫌であった。
僕も渡辺さんも、一杯コーヒーを御馳走になった。
美味しかった!
シャバの味がした!
コーヒー豆の香りが、鼻にツーンと抜けていく。
僕は、つかの間の自由を満喫した。
その時であった。
僕は背中に、刺すような鋭い視線を感じた。
恐る恐る振り返ると、ビックカメラの店員が、僕たちを鬼の形相で睨んでいた。
僕は、その時悟った。
樋口さんはビックカメラの店員たちにも、顔を覚えられていたのである。
さすがに十年も通えば、顔の一つや二つ、覚えられるだろう。
僕たち三人は、店員と目を合わせない様にして、コーヒーカップを片手に、すごすごとビックカメラを後にして、帰路に着いた。