入院闘病記(閉鎖病棟) 闇の支配者、現る 第3話
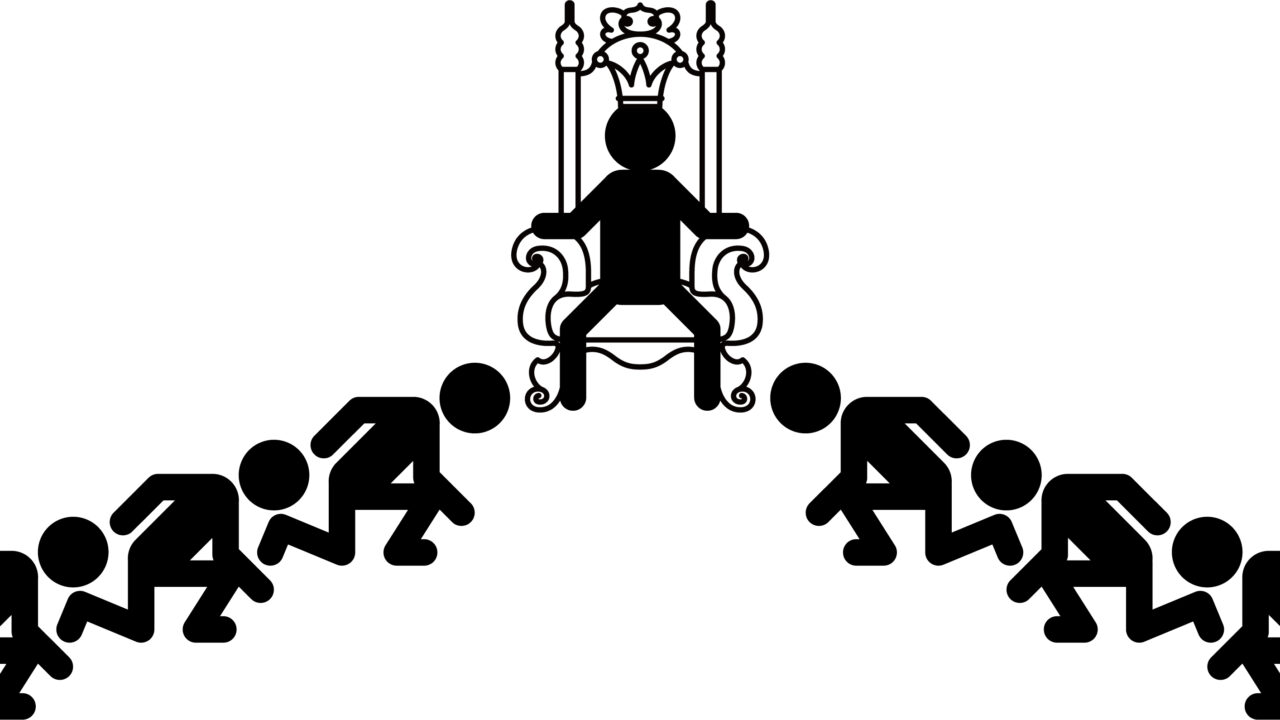
入院四日目の朝、僕は、死臭漂う保護室から、八人の大部屋に移された。この頃、僕は大分落ち着きを取り戻していた。しかし、まだ病識は無く、オナニーを強要して来る幻聴は、毎晩僕を苦しめた。
この時、僕は性の奴隷と化していた。
ある日、僕が一人で食堂の椅子に座って考え事をしていると、遠くの方から鋭い視線を感じた。
何気なくそちらの方を見ると、髪は金髪、眼光鋭く、上は白のタンクトップ、下は赤のジャージで決めた、一見ヤンキー風の男がこちらを睨んでいた。
男は、僕と視線が合うと席を立ち、こちらに向かって歩いてきた。
彼は僕の目の前に来ると、右手を出して、「俺、鈴木圭吾。よろしく!」と、握手を求めてきた。
僕は反射的に右手を出して、握手に応じ、「よろしくお願いします」と、挨拶を交わした。
「この病院のことで何か分からないことがあったら、何でも聞いて」
「はい」
「俺、強迫性障害で二か月前から、入院してるんだ。君、名前何て言うの?」
「ひでまるです。僕、在日韓国人三世です。幻聴、被害妄想が酷くて、医療保護入院しました。今日で四日目です」
「はは、そうなんだ。ま、お互いボチボチやっていこうや!」
「はい」
それだけ言うと、鈴木さんはその場を去って行った。
何か、人を威圧し、不快にさせる雰囲気を持った嫌な奴、それが鈴木さんに対する、僕の第一印象だった。
その日を境に、鈴木さんは事あるごとに、僕に絡んで来た。
彼はおしゃべり好きで、人懐っこかった。
「ねえ、ひでまるさん、退院したら、女の子集めて合コンしようよ!」
「ねえ、ひでまるさんは彼女とかいるの?」
「ねえ、ひでまるさんって、どんな女の子が好みなの?」
鈴木さんのおしゃべりは、延々と続いた。次第に僕は、鈴木さんを避ける様になっていった。鈴木さんの部屋は、僕の隣の大部屋だったが、事あるごとに僕に纏わりついてきた。
「ねえ、ひでまるさんの女友達、紹介してよ」
鈴木さんの頭の中は、二四時間女の事しか無い様だ。僕があからさまに鈴木さんを避け始めると、鈴木さんは僕を中傷し、圧力を掛けてきた。
「ひでまるさんって禿てるよね!全体的に、髪が薄いよね!将来、やばいよ!」
それは、紛れもないイジメであった。
僕は、鈴木圭吾の洗礼を受けながらも、日一日と閉鎖病棟に馴染んでいった。
保護室から漏れ聞こえる意味不明な奇声、ナースステーションから聴こえる美人看護師たちの軽やかな雑談、弁護士を呼べと暴れ回る患者達等、全てのものを真っ白いコンクリートの壁が、容赦無く密閉された空間の中に包み込んでいた。
僕はそこから逃げ出すすべを、何も持ち合わせていなかった。
全くの無力であった。
閉鎖病棟に閉じ込められて一週間位経った頃、自分はこのままこのコンクリートの檻の中で、閉じ込められたまま死んでいくのでは無いかと思った。
その時、何とも言えない大きな恐怖に襲われた。
気が付いたら、ナースステーション横に設置されている公衆電話で、実家の母に電話を掛けていた。
週に二回、凄く恥ずかしい思いをする日がある。
火曜日と金曜日のお風呂の日だ。
脱衣所での着替えから入浴まで、全て看護助手の監視付きである。
僕のいる三階の閉鎖病棟には、青木一臣というダンディーなおじさんと、前田祥子という可愛い癒し系の女の子が勤務していた。
この前田祥子さんに、着替えから入浴からオチンチンを洗うところまで、全て見られるのである。
僕は自分のオチンチンを見られるのが嫌で、死ぬほど恥ずかしかった。
僕は体を洗うのもそこそこに、湯船の中に逃げ込んだ。五十度近い湯船の中に三分も浸かっていれば、もう熱くて限界である。僕は茹でだこの様に顔を赤くして湯船から飛び出ると、脱衣場へと逃げ込んだ。
僕は、前田さんの刺すような視線を背中で感じながら、パンツを手早く履いた。
振り向くと、前田さんと目が合う。
「いい湯だった?」
「はい」
僕は手短に答え、頬を赤らめた。
とある風呂の日。
僕が湯船に浸かっていると、鈴木さんがお風呂に入って来た。
「よう、ひでまるさん、元気?俺は絶好調だよ!今度、女の子と合コンしようよ!」
鈴木さんは、相変わらずのノリだった。
「ひでまるさん、俺、退院が近いんだ。退院しても、お互いに連絡取り合おうね!」
「うん、いいよ。分かった」
「ひでまるさん、可愛い顔してるから、女の子にモテるでしょう?」
「いや、そんなこと無いよ」
本当に女の話ばかりである。
閉鎖病棟の檻に閉じ込められた当初から、鈴木さんは執拗に、僕に絡んで来た。僕が嫌がると、僕を誹謗中傷して圧力を掛けてきた。食堂で、休憩室で、部屋で、「ハゲ!ハゲ!」と、無意味に大声を張り上げるのだ。
その度に、僕は深く傷ついた。
紛れもなく、僕はイジメにあっていた。鈴木さんは、悪徳ヤンキーそのものであった。
とにかく、暇があれば僕に、絡んで来た。
鈴木さんは、三階閉鎖病棟の闇の支配者と化していた。
毎日病棟内を、子分を連れて、練り歩いていた。
僕は次第に、鈴木さんのことを怖れる様になっていった。
















