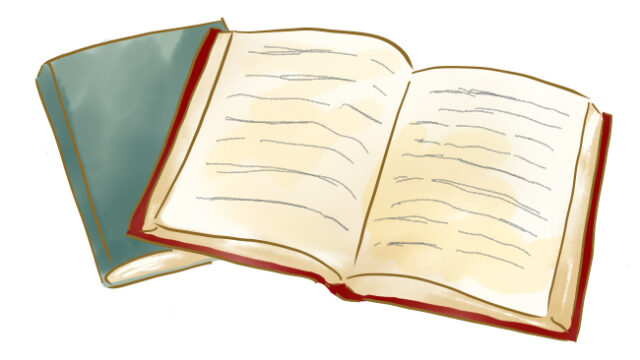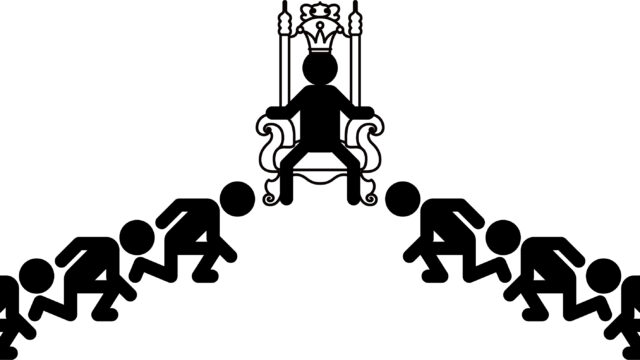入院闘病記(閉鎖病棟) 美魔女、小川尚子 第17話

池田病院三階閉鎖病棟の消灯は、夜9時である。
消灯すると、各部屋の全ての電灯が消され、三階は暗闇に包まれる。
オレンジ色の蛍光灯が、うっすらと長い廊下を照らしている。
この絶望の暗闇の中で、煌々と明るい光を放っているのが、ナースステーションである。
夜九時の消灯後、ナースステーションには、夜勤の看護師が待機しているため、夜どうし灯りが灯っているのである。
夜勤の看護師たちは、眠い目を擦りながら、暇を持て余している。
僕が楽しみにしている日があった。
それは、小川尚子さんの夜勤の日だ。
僕はこの日をワクワクしながら、一日千秋の思いで待っていた。
そして待ちに待った、小川さんの夜勤の日がやってきた。
僕は深夜二時まで待って、行動を起こした。
僕は布団からそっと抜け出し、スリッパを履いて、廊下に出た。
小川さんと何を話そうか考えながら、足早にナースステーションへと向かった。
やはり、女は熟女に限る。四十代から五十代位。
美熟女は、存在しているだけで罪深い。
小川尚子……何て良い女なんだ……。
僕は、ナースステーションの扉を、軽く二回ノックした。
「はーい」
小川さんの明るい声が、深夜の闇の中に、響き渡る。
「ひでまるです。ちょっとお話があって」
「はーい。どうぞ、入って」
小川さんは僕を、ナースステーションの中に招き入れ、椅子を勧めてくれた。
深夜二時過ぎ、小川さんとツーショット成立!
「小川さん、夜勤お疲れ様です。もう二時、回ってますよ。眠くないですか?」
「もう、馴れっこになっちゃったわよ。患者さん達に、いつ何が起きるか分からないから、緊張して眠けも吹き飛んじゃうわよ。ひでまる君も、こんな時間にナースステーションに来るところ見たら、どうやら眠くないみたいね、ふふふ」
僕は小川さんの夜勤の日を、心待ちにしていたことは隠して、小川さんの顔に見とれながら、話を続けた。
「小川さん、看護師になって何年位になるんですか?」
「そうね。今年でかれこれ十五年位になるかしら。嫌だ、歳がばれちゃうわね。こう見えても、もう立派なオバサンなんだから。あまり、オバサンをからかっちゃあ駄目よ」
「仕事で何か、辛い事とかありますか?」
「そうね、未だに採血する時、注射針を肌に刺すのが怖いかしら」
「あ、何かそれ、凄く良く分かります」
僕は真夜中の二時過ぎ、小川さんと何気ない雑談を交わしながら、幸せの絶頂にいた。
この頃僕は、小川さんに夢中になっていた。
小川さんのおっかけだった。
しかし、この様な状況になった原因は、小川さんの方にあった。
僕が入院してまだ日が浅い頃、何かにつけて小川さんは、僕に話し掛けてきた。
話を重ねる内に、僕は徐々に、小川さんに心を惹かれる様になった。
僕はこの頃、小川さんと付き合って、いずれは結婚するんだという妄想を、強く持っていた。
今日、夜勤の小川さんを捕まえたのも、そのことをはっきりさせる為だった。
僕は雑談を切り上げると、問題の核心を突いた。
「小川さんは、結婚してるんですか?」
僕は質問するや否や、急に息苦しくなってきた。
急に、部屋の中の酸素濃度が、希薄になった様な気がした。
心臓が、バクバクと早鐘を打った。
小川さんは、意を決した目で、僕を見つめながら答えた。
「私、結婚してます。子供もいます」
僕はその答えを聞いた瞬間、絶望の淵から突き落とされると同時に、現実を思い知った。
本気になった自分が、馬鹿だった。
三十七才、無職、童貞、ひきこもり、統合失調症患者を、本気で好きになる女などいないのである。
こんな綺麗な人が、本気で自分なんかを相手にするはずがなかった。
僕は小川尚子の掌の上で、踊らされていただけだった。
僕は、窓の外に目を向けた。
夜の闇が、更に深まったように感じた。
僕は瞬時に気持ちを入れ替えて、小川さんに質問した。
「小川さん、趣味は何ですか?」
「趣味?ねえ、そんなに私を、質問攻めにしないで。今度は、私からひでまる君に質問させて」
小川さんの顔つきが、美熟女から美魔女に変わった。
その豹変ぶりに、僕は怯んでしまった。
「ねえ、ひでまる君は恋人いるの?」
「いや、いないです」
「じゃあ、今は右手が恋人なんだ。ふふふ、オナニー好き?」
僕は、小川さんのあまりにストレートな質問に、面食らってしまった。
「オナニーですか……。はい……好きです」
「男の人って、毎日オナニーしないと我慢できないものなの?」
「いや、そんなことは無いと思いますけど」
「ひでまる君は毎日してるの?」
「いや、毎日では無いですけど。週に一回位です」
「へえー、そうなんだ!ねえ、ひでまる君、私の事をオカズにして、抜いてるでしょう?」
僕は、あまりにも図星だったため、言葉に詰まってしまった。
「あまり、私で抜いちゃあ駄目よ。今度からお金、取ろうかしら」
小川さんはさらりと言ってのけると、飲みかけのお茶に手を伸ばした。
その横顔が、一瞬悪魔に見えた。
到底、僕の太刀打ちできる相手ではないと思った。