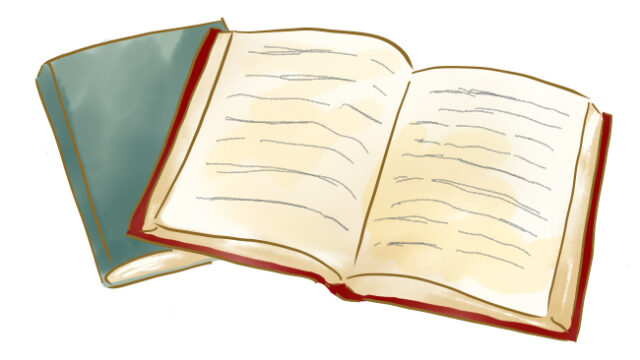入院闘病記(閉鎖病棟) 深夜の徘徊 第9話

僕は散歩を毎日の日課としていた。
散歩といっても、外の道路を歩く訳では無い。
そんな贅沢、閉鎖病棟の住人である僕に、許されるはずはない。
三階の閉鎖病棟内を、散歩しているのである。
東病棟から始まって西病棟に至るまで、隅から隅まで隈なく歩いた。
食事の後の休憩時間、就寝前の休憩時間、夜に寝付けないときは深夜も、歩いて歩いて歩き続けた。
僕はこの時期、精神的にかなり追い込まれていて、この散歩(徘徊?)が良い気分転換になった。
一日に三時間は歩いていたと思う。
気が付くと、履いていたスリッパはボロボロになり、踵は岩の様に固くなっていた。
ここ三階閉鎖病棟は、東病棟と西病棟の二つからなっている。
僕の部屋は東病棟の一番奥の、八人の大部屋だった。
廊下の一番奥には、二人位が座れる、小さなソファーが置かれていた。
廊下を挟んで、左右に部屋が並んでいる。
廊下を真っすぐ進み、左右にそれぞれ三つずつある部屋を過ぎると、左手に東ナースステーション、右手に休憩室がある。
休憩室にはテレビがあり、喫煙所がある。
東ナースステーションには、二十四時間灯りが灯っている。
中では看護師たちが、常に忙しそうに動き回っていた。
そして、休憩室の横に食堂がある。二、三十人位は食事が出来る、大きな食堂である。
東ナースステーションを左へ曲がると、西病棟に向けて、細い廊下が伸びている。
その廊下の左側に、保護室が三部屋並んでいる。
奇声を上げる者、扉を激しく叩く者、大声で泣きわめく者、色んな人たちが保護室に閉じ込められていた。
保護室の扉は、刑務所の檻の様に、固く施錠されている。
固く大きい鉄の鍵が、患者たちの夢や希望、そして人権までをも奪い去っていく。
一直線に真っすぐ伸びる、細い廊下の突き当りが、西病棟の休憩室である。
そして、そこから左右に廊下が伸びている。
右に曲がると直ぐに、西ナースステーションがある。
扉の脇にポツンと寂しく、赤い公衆電話が置かれている。
外界へ繋がる唯一のアイテムだ。
僕の散歩は、東病棟から始まり西病棟の隅まで、完全制覇する。
だから僕は、西病棟の人達とも顔馴染みになっていた。
とある日の夜、僕は何故か上手く寝付けずに、また散歩に出ることにした。
腕時計を見ると、深夜零時を回っていた。
僕は部屋の中の人達を起こさない様に、そっと廊下に出た。
ジメジメと、蒸し暑い夜だった。
僕は廊下を突っ切って、真っすぐ進んだ。
左手に、東ナースステーションの灯りが見えてきた。
僕はコッソリ、ナースステーション内を覗き見た。
部屋の中では、橋本和男さんが深夜零時を回っているというのに、ロッカーの中の患者のカルテを、整理していた。
机の上には、マンガ本、コンビニ弁当、缶コーヒー、リポビタンDが置かれていた。
僕は橋本さんが、リポビタンDの愛飲者であることを知って、妙な親近感を覚えた。
(この人も、カフェインに毒された人なんだ……)
と、思うと、何だか嬉しくなった。
僕は橋本さんにバレない様に、ナースステーションを通り過ぎると、廊下を左へ曲がり、西病棟へと向かった。
途中、保護室から、
「弁護士を呼べ!弁護士を呼べ!訴えてやる!」
という叫び声が聞こえた。
廊下を真っすぐ進むと、西病棟の休憩室が見えてきた。
すると、休憩室前の廊下の床の上に、誰か胡坐をかいて座っていた。
辺りには、無数の新聞広告が散乱していた。
薄暗い灯りの中、近づいて良く見ると、西病棟の泉潤一郎君だった。
軽い知的障がいのある若者だった。
泉君は僕と目が合うと、真剣な眼差しで叫んだ。
「俺、就職する!絶対に就職する!何が何でも就職する!」
辺りに散乱している紙切れを良く見ると、全部求人広告だった。
「俺、就職する!絶対に就職する!みんな、見てろ!」
泉君は同じ言葉を、何度も何度も繰り返した。
こんな深夜に、廊下の床で独り、就職活動をする泉君を見て、僕は胸に熱いものがこみ上げて来た。
泉君が無事、病院を退院して就職できることを願いつつ、僕は廊下を引き返した。
その夜、僕の脳裏から、泉君の姿が消えることは無かった。